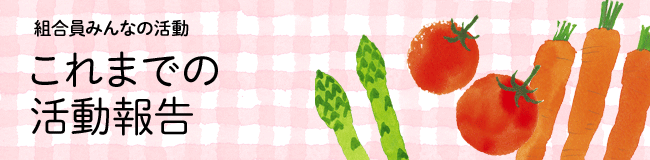講習会&学習会報告
組合員活動情報紙 『ワォ』 2004年12月号より
東都生協が2004年8月28日、さんぼんすぎセンターで開催した平和のつどいでの「国境なき医師団」の臼井律郎医師の講演内容をご報告します。
国境なき医師団(MSF)は、営利を目的としない国際的な民間援助団体で、1971年フランスで設立され、医療援助を専門に活動しています、年間約 3,000人の医師、看護師、助産師らが世界約80カ国で援助活動を行っています。
国境なき医師団日本は、1992年に設立され、2002年7月認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)として認定を受けました。
日本副会長の臼井医師は、アフガニスタンなど実際行かれた国で銃で撃たれた
少女の治療、字を読めない人に薬を飲ます苦労、ストリートチルドレンへの教育、AIDSへの啓蒙活動など、途上国の貧困の現実まで語られました。
当日は、現地での報告をスクリーンに映しての分かりやすい説明となり、1時間の
時間では、到底語り尽くせない内容となりました。
講演当日のテープがあります、聞きたい方は組織運営部までお問い合わせください。
2004年10月1日、東京都生協連会館で、早稲田大学の馬奈木厳太郎先生を講師に23人の参加で有事法制学習会が開催されました。
2001.9.11以降のアメリカの外交・安全保障政策と有事法制の整備の流れの説明や、米軍の弾薬を日本の民間輸送業者が運ぶことは、PKO等協力法第26条や周辺事態法9条によってすでに行われています。
同年6月14日成立の「国民保護法」には、国民の役割について「必要な協力に努める」と自発的な意思に委ねる一方、避難のための土地や家屋の使用、食品や医薬品などの物資保管などで都道府県知事の強制権を認める私権制限に踏み込まれています。
(生協の食品や車両も収用の対象となりえます)違反者には罰則も科せられます。
「有事」が想定する社会は個人よりも国家が優先される社会です。ところが基本的人権を制約することは憲法に反するだけでなく、国際法上も問題があるとのことでした。
東都生協では、引き続き学習を進めていきます。