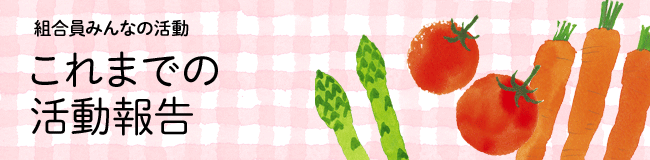消費者と畜産農家の願いをつなぐ緊急集会を開催
国内の日本の農畜産業を守る力に...。いままでも、これからも、日本の畜産物を食べ続けたい
2010.07.28
カテゴリ 食と農
日本大学 生物資源科学部准教授 |
東都生協組合員から生産者へ |
生産者からも消費者へ |
東都生協組合員から届いた |
「日本の畜産業が抱える悩み」と題した日本大学・生物資源科学部准教授・早川治氏の基調講演に続き、生産と消費の現場からメッセージを交換。生産者側からはこれからも消費者の安全・安心への願いに応えた国産畜産物を届けていくこと、消費者からは利用を通じて生産者を強く支援していく熱い決意が交わされました。
締めくくりに「この危機を乗り越え、守っていこう! 日本の畜産」とした緊急アピールが採択されました。
緊急集会概要
冒頭、東都生協の庭野吉也理事長から開催趣旨を説明。
日本の畜産農家はいま、増え続ける輸入肉や飼料の高騰、重労働や高齢化などの問題を抱え、存続の危機に瀕しながらも、消費者の願いに応えるため一所懸命に食卓に日本の畜産物を届けています。
庭野理事長は今回の集会を、日本の畜産の現状を消費者が再確認し、消費者が国内産の農畜産物を食べ続けていく決意と日本の畜産生産者への激励のメッセージを強く発信していくために開催したと述べました。
続いて、日本大学の早川治准教授(生物資源学部 国際地域開発学科)より「日本の畜産業が抱える悩み」と題し基調講演を行いました。
まず穀物価格の高騰が日本の畜産業へ及ぼす影響について解説。
畜産の産出額は農業総産出額の約3割を占める重要な産業であるにもかかわらず、牛乳・乳製品の消費低迷や肉類の輸入拡大、とりわけ生産コスト増大の要因となる世界穀物市場への投機資金の関与は、飼料を外国に依存している日本にとって、日本の畜産業の根幹を揺るがす大きな問題だと指摘しました。
また、口蹄疫をはじめ家畜伝染病についても言及。宮崎県の口蹄疫被害で家畜を処分せざるを得なかった牧場の再生には豚で1年半以上、牛で2年半~3年はかかる長い道のりになるということです。
生産者と組合員のリレートークでは、生産者など畜産関係者・東都生協の組合員9人がそれぞれの思いを会場に投げ掛けました。
生産者からは、「BSEや鳥インフルエンザの時もそうだったが、風評被害に対し、また検査を待つ間の数日は言い表せないような気持ちで過ごしていたが、生協だけは買い支えてくれた。これらを励みにし、生産を続けたい」「穀物相場の高騰や口蹄疫でさらに厳しさを増し、このままでは日本の畜産業は無くなってしまう。でもこんな苦しさの中、組合員の皆さんに買い支えていただいていることには感謝の気持ちでいっぱいです」との思いが語られました。
これに対し消費者側の東都生協組合員からは、「日本の畜産は私たちの手で守っていきたい。みんなが応援しています。がんばってください」「買い支えることで、自分たちの食卓を守り、国内の生産者を支援していきたい。これからも東都生協の畜産品を利用し続けます」との激励のメッセージが贈られました。
宮崎県内で東都生協の産直肉「霧島黒豚」を生産する産直産地・キリシマドリームファーム(林兼産業株式会社)からは、現地の詳細な状況を報告。同産地では口蹄疫の被害はないものの、先が見えない辛い状態が続く中、農場に出入りする車両の制限や徹底した消毒など、全従業員が一丸となって厳重な防疫体制を敷いている、との報告がありました。
緊急集会の締めくくりに、「この危機を乗り越えて、守っていこう! 日本の畜産」とした緊急アピールが採択され、正しい情報を共有化し、日本の畜産業の存続を願う参加者の大きな拍手で確認されました。
東都生協はこれからも日本の畜産業を応援します
なお、集会の中で6月~7月に東都生協が実施した「口蹄疫被害に対する支援募金」に、これまで約700万円もの支援が寄せられたことが報告されました。届いた励ましのメッセージカードが230通。カードは会場入り口に掲げられ、立ち止まって見入る参加者もみられました。
東都生協は、これまでも国産の精肉や、国産肉原料の加工食品を組合員に提供し、利用を通じて日本の畜産業を応援してきました。また、「安全な国産の農畜産物を食べ続けたい」との願いの下、産直産地と共に「食の未来づくり運動」をはじめとした取り組みを進めています。
いま私たち消費者に求められていることは、日本の畜産農家の現状を正しく知り、国産の牛肉、豚肉、鶏肉、そして牛乳やたまごを買い支えていくことであり、産直畜産産地と「食の未来づくり運動」を一緒に推進していくことをあらためて確認しました。